2010年07月10日
平成22年度 高松市地域ゆめづくり提案事業 その壱
さて、最近の馬車馬人生に拍車をかけたかのような新規事業の着手で
バタバタの毎日を送っています。
今夜も会議ですが・・・何か?
の勢いです。
その一つである、『高松市地域ゆめづくり提案事業』。
去年もだらだらと東谷の地域振興に関するプレゼンの内容を記しました。
今回も記します。
去年のプレゼンの資料を、今年利用してくれた校区もあるということで、
地域にいいことはなるべく共用すればいいじゃん!!的なノリですが、
だらだらに付き合って、1年後にどんな結果が生み出せるのか見守っていてください。
ではでは・・・
平成22年6月26日(土) 13:20~川東校区コミュニティ協議会提案
『竹採りマルチチャレンジプロジェクト』←センター長命名
通称『竹マルプロジェクト』←私命名
スタートです!!
今年もまたやってきました!川東校区の鎌田です。
サッカー観戦の週末でお疲れだとは思いますが、どうぞ最後まで眠らないでお付き合い下さい。
川東校区が本年度 提案する夢づくり提案事業は…
竹採りマルチチャレンジ プロジェクト
通称 竹マルプロジェクトと名づけまして
放置竹林の問題に取組むということをベースに
いろいろなことにチャレンジしてみよう!!
ということになりました。

まず、どうして竹問題を取り上げたのか説明し
そして、その現状と課題を考察するとともに 原因を追究し
考えられるすべての解決策を提示しました。
そのなかで、自分達で取組めるだろう事業を提案し
それによる期待効果を説明していきます。

早速、チャレンジしておりますのが、
プロジェクト名をもじり作成したマスコットキャラクターの
『竹マル君』です。
では、事業の説明にはいります。

なぜ、今竹なのか…。
それは東谷地区の現状にあります。
人口は 年々確実に減少し
日々高齢化の一途を辿っております。
細長い盆地を取り囲む山々には、竹がはびこり
地区住民で年に2回から3回 取組む整備作業では
なかなか竹の駆除に追いつけないのが現状です。

コミュニティプラン内では地域振興と
山林・田畑の荒廃の改善ということで記してあります。
地域で持て余している課題について
地域コミュニティが
継続的に
みんなで『ゆめの解決策』を探そう!!
ということで頑張りたいと思います。

さて、その地域で持て余している現状として 田畑への侵入があります。
写真の黄色ラインは
その昔、田んぼの畦であった所です。

道路にも竹は生えて亀裂が入り
路肩は崩れやすくなります。
また、右手の写真ですが、
竹が倒れて手前に傾いています。
竹の根は浅く張るので
地すべりを起こしやすく、とても危険です。
更に雪が降ると 雪の重みで竹は倒れ
車が通れないことが多々あります。

この写真は、5年程まえまでは
向かいの山が見えていたのですが
ご覧の通り、現在では空も見えないくらい 竹が密集しております。

資源として
その昔、タケノコの出荷も 多くの農家でしていたのですが、
高齢化と 山間部の竹やぶで
掘るのも一苦労ということで
現在、数件しか出荷はしていません。

東谷地区では平成11年から東谷炭生産組合で
竹炭と竹酢液を生産販売しています。
こちらの活動は、販売が主な目的ではなく
高齢者の活動促進が目的で作られた組合で
現状は高齢化しすぎて困っているそうです。
商品は校区文化祭やふれあい交流事業のバザー等で販売しております。
その弐に続く
バタバタの毎日を送っています。
今夜も会議ですが・・・何か?
の勢いです。
その一つである、『高松市地域ゆめづくり提案事業』。
去年もだらだらと東谷の地域振興に関するプレゼンの内容を記しました。
今回も記します。
去年のプレゼンの資料を、今年利用してくれた校区もあるということで、
地域にいいことはなるべく共用すればいいじゃん!!的なノリですが、
だらだらに付き合って、1年後にどんな結果が生み出せるのか見守っていてください。
ではでは・・・
平成22年6月26日(土) 13:20~川東校区コミュニティ協議会提案
『竹採りマルチチャレンジプロジェクト』←センター長命名
通称『竹マルプロジェクト』←私命名
スタートです!!
今年もまたやってきました!川東校区の鎌田です。
サッカー観戦の週末でお疲れだとは思いますが、どうぞ最後まで眠らないでお付き合い下さい。
川東校区が本年度 提案する夢づくり提案事業は…
竹採りマルチチャレンジ プロジェクト
通称 竹マルプロジェクトと名づけまして
放置竹林の問題に取組むということをベースに
いろいろなことにチャレンジしてみよう!!
ということになりました。
まず、どうして竹問題を取り上げたのか説明し
そして、その現状と課題を考察するとともに 原因を追究し
考えられるすべての解決策を提示しました。
そのなかで、自分達で取組めるだろう事業を提案し
それによる期待効果を説明していきます。
早速、チャレンジしておりますのが、
プロジェクト名をもじり作成したマスコットキャラクターの
『竹マル君』です。
では、事業の説明にはいります。
なぜ、今竹なのか…。
それは東谷地区の現状にあります。
人口は 年々確実に減少し
日々高齢化の一途を辿っております。
細長い盆地を取り囲む山々には、竹がはびこり
地区住民で年に2回から3回 取組む整備作業では
なかなか竹の駆除に追いつけないのが現状です。
コミュニティプラン内では地域振興と
山林・田畑の荒廃の改善ということで記してあります。
地域で持て余している課題について
地域コミュニティが
継続的に
みんなで『ゆめの解決策』を探そう!!
ということで頑張りたいと思います。
さて、その地域で持て余している現状として 田畑への侵入があります。
写真の黄色ラインは
その昔、田んぼの畦であった所です。
道路にも竹は生えて亀裂が入り
路肩は崩れやすくなります。
また、右手の写真ですが、
竹が倒れて手前に傾いています。
竹の根は浅く張るので
地すべりを起こしやすく、とても危険です。
更に雪が降ると 雪の重みで竹は倒れ
車が通れないことが多々あります。
この写真は、5年程まえまでは
向かいの山が見えていたのですが
ご覧の通り、現在では空も見えないくらい 竹が密集しております。
資源として
その昔、タケノコの出荷も 多くの農家でしていたのですが、
高齢化と 山間部の竹やぶで
掘るのも一苦労ということで
現在、数件しか出荷はしていません。
東谷地区では平成11年から東谷炭生産組合で
竹炭と竹酢液を生産販売しています。
こちらの活動は、販売が主な目的ではなく
高齢者の活動促進が目的で作られた組合で
現状は高齢化しすぎて困っているそうです。
商品は校区文化祭やふれあい交流事業のバザー等で販売しております。
その弐に続く
2010年07月10日
平成22年度 高松市地域ゆめづくり提案事業 その弐
地域ゆめづくり提案事業プレゼン その弐であります。

放置竹林拡大の要因をまとめますと
竹林の所有者の高齢化に伴い
重労働である管理作業や 農業の担い手不足により
竹林の管理ができなくなったことや
中国などの外国産のタケノコが輸入されるようになり、
国産タケノコの出荷量が減るなど
竹が利用されなくなったということが原因と考えられます。

そこで考えられる解決策として 第一に竹林整備作業があげられます。
その長所は 切れば切っただけ景観は良くなり
3年間連続して頑張れば、ほとんど太い竹が生えなくなります。
また、竹を資源として必要としているところもあり
買い取ってくれるというケースもあります。
逆に短所としてあげられるのは、傾斜のきつい場所での作業は危険が伴い
なかなか 新規の作業ボランティアを集めることが困難です
また、切った後の竹の運搬や枝葉の処理などが大変で
その場に切り倒し 腐るのを待つだけということも
もちろん、切り出した竹を利用しなければ
折角の 資源も無駄になります。
それにかかる経費は人件費に保険料や運搬費等が必要になります。

二つ目に食品や竹チップや竹パウダーとしての
活用をしようと考えた場合の長所は
廃棄していた竹を有効利用でき
生活をより豊かに そして ゴミ問題などの環境 食生活 農業等に貢献できます。
しかし 逆に、加工しても竹を大量に消費できないこともあり
手間と費用がかかるのが短所の一つです。
また、効果がでるまでに時間がかかり その効果が見えにくい点も課題です。
そのためにかかる経費は数百万とかかれているとおり
設備投資に多額な資金が必要です。

こちらは参考プロジェクトとして、
香川県東部林業事務所の河野氏が 東谷のために作ってくれたモデルケースです。
整備作業で出た竹を販売し
得られた収益をまた整備作業等に還元し 循環させるというプロジェクトです。
これにより、行政からの支援と協働の可能性の一つが見えてきました。

いろいろな解決策を模索した上で、
校区で取組むための目標として
現在実行している整備作業等の環境保全事業の改善や継続
生ゴミの減量など 竹資源の有効活用方を実験し、
自分達の目で確認 その効用を紹介し普及させる。
また、次世代である子ども達や地域の人たちにもよびかけ
竹の面白さや親しむ機会を設けること。
そして、経費の面ですが
初年度は竹に対する正しい知識や、新たな農法等の基礎知識をみにつけたりと
基礎固めの年度とし 40万円を計上し実施します。
(正確には370,000円+東谷コミュニティ部会より29,000円=399,000円)
これを元手に 地域の資源を生かし放置竹林を
宝の山へと変える第一歩にしたいと考えています。

その一歩を踏み出すにあたって、プロジェクトの組織編制をします。
本部が全体の進捗状況を把握し指示を出します
その下に
環境保全事業部
開発事業部
広報事業部が
それぞれ役割分担し、連携をとりながら活動をします。

環境保全事業は主に祇王山の整備事業や
主要道路沿いの竹林の整備をし
個人所有の放置竹林の整備等に手を入れていきます。

また、炭生産組合の材料である竹の伐採や
先進地の持つノウハウを活かし
竹を資源として取引してくれるところと協力
それにより上がった収益を里山整備に活用したりと考えています。
この事業には 年間予算の約10%の費用を充てます。

そして、一番目玉である 開発事業です。
地域に普及されていない 竹の利用を研究し
農産品の品質や収穫量にどれだけ影響するものなのか実証します。
また、それにより上がった収益は
竹マルプロジェクトに活用したいと考えています。
この事業には 年間予算の 約50%の費用を充てます。

こちらは、開発事業の中でも特に環境問題に視点をおいた
生ゴミの減量に関する開発です。
竹パウダーを利用して生ゴミを減らし
更に、それが堆肥として利用できるという実験です。
高松市消費者団体連絡協議会が推奨しているピートモスとの比較も考えています。
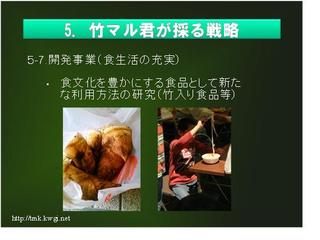
開発の中で食品に関しては 繊維質の竹は体にも良く
うどんやそば、クッキー パンといったように
様々な利用法があるようです。

そして、年間予算の20%を充てて
広報事業部では 竹に親しむという文化を子ども達に伝えるため
学校と等と連携しイベントを開催したり
今どんな事業をやっているのか
どんな実証結果がでたのか
また、開催されるイベントの募集などを
年3回発行の広報とインターネットでの情報発信を考えています。
すでに、インターネットでの情報発信は始めておりますので
竹マルくん…『マル』はカタカナで検索してみてください。
(すでに、このブログのお気に入りには入れてますので、ぽちっとしていただければ飛びます)

竹マルプロジェクトの期待効果としては
放置竹林の減少 荒廃した田畑の雑草管理等の環境保全や
竹を原料とした新たなる製品の開発・販売により持続していけるという可能性があるということ。
また、竹を使った農法等で 農産品の品質向上や収穫量の増加が見込めたり
環境問題を取り上げた 生ゴミの減量化や
竹を使った遊びなど 文化の継承等の期待効果があり
コミュニティの基本部分である
自分達の地域の問題にコミュニティ協議会がどう係って、問題解決に導くかというスキルアップを目標とし
そして、困ったときはお互い様…の精神で、一つの問題に校区全体で取組むという地域の一体感を醸成できるのではという期待があり
イベント等を通して、市民が誰でも気軽に竹に関するノウハウを身につけられ
尚且つ、同じ問題を抱える地区同士情報交換や勉強会が出来ればいいなぁ
と考えております。

夢の実現への一歩として この事業を提案させていただきました。
プロジェクトと共に 竹マル君も育てていきたいと思っています。
竹マル君を どうぞよろしくお願いします。
御静聴 ありがとうございました。
放置竹林拡大の要因をまとめますと
竹林の所有者の高齢化に伴い
重労働である管理作業や 農業の担い手不足により
竹林の管理ができなくなったことや
中国などの外国産のタケノコが輸入されるようになり、
国産タケノコの出荷量が減るなど
竹が利用されなくなったということが原因と考えられます。
そこで考えられる解決策として 第一に竹林整備作業があげられます。
その長所は 切れば切っただけ景観は良くなり
3年間連続して頑張れば、ほとんど太い竹が生えなくなります。
また、竹を資源として必要としているところもあり
買い取ってくれるというケースもあります。
逆に短所としてあげられるのは、傾斜のきつい場所での作業は危険が伴い
なかなか 新規の作業ボランティアを集めることが困難です
また、切った後の竹の運搬や枝葉の処理などが大変で
その場に切り倒し 腐るのを待つだけということも
もちろん、切り出した竹を利用しなければ
折角の 資源も無駄になります。
それにかかる経費は人件費に保険料や運搬費等が必要になります。
二つ目に食品や竹チップや竹パウダーとしての
活用をしようと考えた場合の長所は
廃棄していた竹を有効利用でき
生活をより豊かに そして ゴミ問題などの環境 食生活 農業等に貢献できます。
しかし 逆に、加工しても竹を大量に消費できないこともあり
手間と費用がかかるのが短所の一つです。
また、効果がでるまでに時間がかかり その効果が見えにくい点も課題です。
そのためにかかる経費は数百万とかかれているとおり
設備投資に多額な資金が必要です。
こちらは参考プロジェクトとして、
香川県東部林業事務所の河野氏が 東谷のために作ってくれたモデルケースです。
整備作業で出た竹を販売し
得られた収益をまた整備作業等に還元し 循環させるというプロジェクトです。
これにより、行政からの支援と協働の可能性の一つが見えてきました。
いろいろな解決策を模索した上で、
校区で取組むための目標として
現在実行している整備作業等の環境保全事業の改善や継続
生ゴミの減量など 竹資源の有効活用方を実験し、
自分達の目で確認 その効用を紹介し普及させる。
また、次世代である子ども達や地域の人たちにもよびかけ
竹の面白さや親しむ機会を設けること。
そして、経費の面ですが
初年度は竹に対する正しい知識や、新たな農法等の基礎知識をみにつけたりと
基礎固めの年度とし 40万円を計上し実施します。
(正確には370,000円+東谷コミュニティ部会より29,000円=399,000円)
これを元手に 地域の資源を生かし放置竹林を
宝の山へと変える第一歩にしたいと考えています。
その一歩を踏み出すにあたって、プロジェクトの組織編制をします。
本部が全体の進捗状況を把握し指示を出します
その下に
環境保全事業部
開発事業部
広報事業部が
それぞれ役割分担し、連携をとりながら活動をします。
環境保全事業は主に祇王山の整備事業や
主要道路沿いの竹林の整備をし
個人所有の放置竹林の整備等に手を入れていきます。
また、炭生産組合の材料である竹の伐採や
先進地の持つノウハウを活かし
竹を資源として取引してくれるところと協力
それにより上がった収益を里山整備に活用したりと考えています。
この事業には 年間予算の約10%の費用を充てます。
そして、一番目玉である 開発事業です。
地域に普及されていない 竹の利用を研究し
農産品の品質や収穫量にどれだけ影響するものなのか実証します。
また、それにより上がった収益は
竹マルプロジェクトに活用したいと考えています。
この事業には 年間予算の 約50%の費用を充てます。
こちらは、開発事業の中でも特に環境問題に視点をおいた
生ゴミの減量に関する開発です。
竹パウダーを利用して生ゴミを減らし
更に、それが堆肥として利用できるという実験です。
高松市消費者団体連絡協議会が推奨しているピートモスとの比較も考えています。
開発の中で食品に関しては 繊維質の竹は体にも良く
うどんやそば、クッキー パンといったように
様々な利用法があるようです。
そして、年間予算の20%を充てて
広報事業部では 竹に親しむという文化を子ども達に伝えるため
学校と等と連携しイベントを開催したり
今どんな事業をやっているのか
どんな実証結果がでたのか
また、開催されるイベントの募集などを
年3回発行の広報とインターネットでの情報発信を考えています。
すでに、インターネットでの情報発信は始めておりますので
竹マルくん…『マル』はカタカナで検索してみてください。
(すでに、このブログのお気に入りには入れてますので、ぽちっとしていただければ飛びます)
竹マルプロジェクトの期待効果としては
放置竹林の減少 荒廃した田畑の雑草管理等の環境保全や
竹を原料とした新たなる製品の開発・販売により持続していけるという可能性があるということ。
また、竹を使った農法等で 農産品の品質向上や収穫量の増加が見込めたり
環境問題を取り上げた 生ゴミの減量化や
竹を使った遊びなど 文化の継承等の期待効果があり
コミュニティの基本部分である
自分達の地域の問題にコミュニティ協議会がどう係って、問題解決に導くかというスキルアップを目標とし
そして、困ったときはお互い様…の精神で、一つの問題に校区全体で取組むという地域の一体感を醸成できるのではという期待があり
イベント等を通して、市民が誰でも気軽に竹に関するノウハウを身につけられ
尚且つ、同じ問題を抱える地区同士情報交換や勉強会が出来ればいいなぁ
と考えております。
夢の実現への一歩として この事業を提案させていただきました。
プロジェクトと共に 竹マル君も育てていきたいと思っています。
竹マル君を どうぞよろしくお願いします。
御静聴 ありがとうございました。





